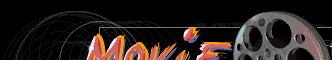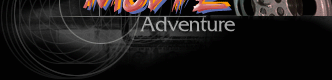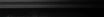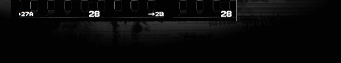映研法度にもあるように、映研は会員全員がシナリオを書く決まりになっていました。最初
の頃は書かなかっただけで、すわ退会処分かとかいう論議が出たくらいの絶対の掟でし
た。春休みには比較的真面目な合宿があって、それがシナリオ決定の場となりました。大
学そのものは年が明ければ、後は1月末の試験が終われば春休みです。その頃に各自が
シナリオを書いて、学生部の印刷機を借りて印刷します。当時はガリ版印刷ではなくて、ボ
ールペン原紙と呼ばれていた緑色の原紙を切るまでが各自の仕事で、印刷は係がすること
になっていました。しかし、「40年」のシナリオは遅れてしまったので、共同原作の先輩が
会社でコピーをしてくれました。 
「40年・・」の脚本はクレジットでは根本鋭という名義になっています。しかし、原作は小川
野清志郎&根本龍一としてあります。正式なタイトルが二転三転して、「い・け・な・い・ルー
ジュマジック」と「十年ロマンス」を混ぜたようなタイトルになってしまったので、原作者の名
前がそれなりの名前になってしまったという訳です。しかし、共同原作といっても先輩の名
前は無理に担ぎ出したようなもので、プロットの段階で二、三、アドバイスをもらった程度でし
た。共同原作に名を連ねられてしまったのは、先輩としては痛し痒しだったでしょう。私とし
ては偉大なる(?)先輩のネームバリューが欲しかったわけで、同じ手は「多摩川節考」の
時にも使ってしまいました。 そもそも、この映画のアイディアは赤塚不二夫の漫画から来ています。初期のバカボンに
よくあったネタで「昨日、国会で決まったから・・」というギャグがありました。街の人たちがバ
カボン親子をだまして笑いものにするというギャグです。それをドリフの大爆笑の「もしも」シ
リーズみたいに発展させたものが基盤にありました。 「もしも、日本でそばを食べることが禁止されて、食べただけで逮捕されるとしたら・・」そ
れが成立するための言い訳を考え、後はそれによって、どう社会が動くかを戯画化し、青春
アクション映画をベースにあらゆる要素をぶちこんで立ち上げた脚本だったのです。本来は
主人公の一夫とカオルが主人公らしくきちんと活躍するストーリーだったのですが、途中で
カオルが病で倒れたという設定になり、ひたすら一夫はその看病に明け暮れて、物語の表
舞台から消えてしまいます。物語は途中からそばを取り締まる政府側の組織と「そばを国民
の口に取り戻す運動」家たちとの争いへとシフトチェンジ。重要な人物らしきキャラクターが
次々と凶弾に倒れる「仁義なき戦い」のスタイルになっていきます。これは「いっそのこと主
人公を無しにしてしまえ。」という原作者・小川野清志郎氏の貴重なアドバイスによるもので
す。 今思うと、この映画最大の欠陥は脚本を書いた私自身が映画化に関して脚本を、もっと書
き込まなかった点にあったと思います。脚本はもっともっと練り込まなくてはならないもので
す。脚本兼監督となってしまうと、どうしても他のスタッフは注文を付けにくかったようです。
改編したのは途中で出て来る刑事とやくざが元親友同士という設定を、やくざの方を女性に
して、二人を元恋人としたくらい。女の子の出番が少ないから、多くした方がいいとアドバイ
スしたのはプロデューサーでした。とにかくその役を女性に替えたのは成功だったと思って
います。人の意見は貪欲に採り入れなくてはいけません。 決定稿が第6稿版となったものの、目立った変更はなかったのです。 |